注文住宅は建売や中古の購入と比べて、やるべきことが多いです。全体の流れを把握せずに手探りで動き出すと、想定より期間がかかり見落としがあるかもしれません。
そこで本記事では、注文住宅を建てる人向けに流れやかかる期間、費用、注意点を解説していきます。これから何十年も満足して住めるマイホームにするため、手順を踏んで堅実に計画を進めていきましょう。
 |
名前 | Kさん |
| 利用したハウスメーカー | 旭化成ホームズ | |
| 物件所在地 | 茨城県 | |
| 住宅購入時期 | 2021年6月 |
※当メディアでは、ユーザーの生の声をお届けするために、商品・サービスの利用者に直接取材を行っています。
 編集部
編集部
目次
注文住宅を建てるまでどのくらいの期間がかかる?

注文住宅を建てる期間は、現在土地があるかないかで大きく変わります。それぞれどの程度の期間がかかるのか、詳しく解説していきます。
土地なしの場合
現状土地なしから注文住宅を建てる場合、引渡しまでの期間は10ヵ月~1年半が目安です。すぐに希望条件を満たす土地が見つかる場合もあれば、希望の土地を見つけるのに長期間かかることもあります。
また、立地がよく割安なところはすぐに売れてしまうため、決断力がないとなかなか土地を決められず、さらに時間がかかってしまうかもしれません。
土地ありの場合
土地が決まっている状態で注文住宅を建てる場合、最短で半年~7ヵ月が目安です。依頼先の業者選びや住宅のプランをすぐに決められれば、スムーズにマイホームを建てられるでしょう。
所有する土地に現在建物があり、解体してから注文住宅を建てる場合は、追加で1~2ヵ月は必要になります。解体業者の選定や建物内部の整理などに時間がかかる場合は、さらに期間がかかるかもしれません。
注文住宅を建てる流れ
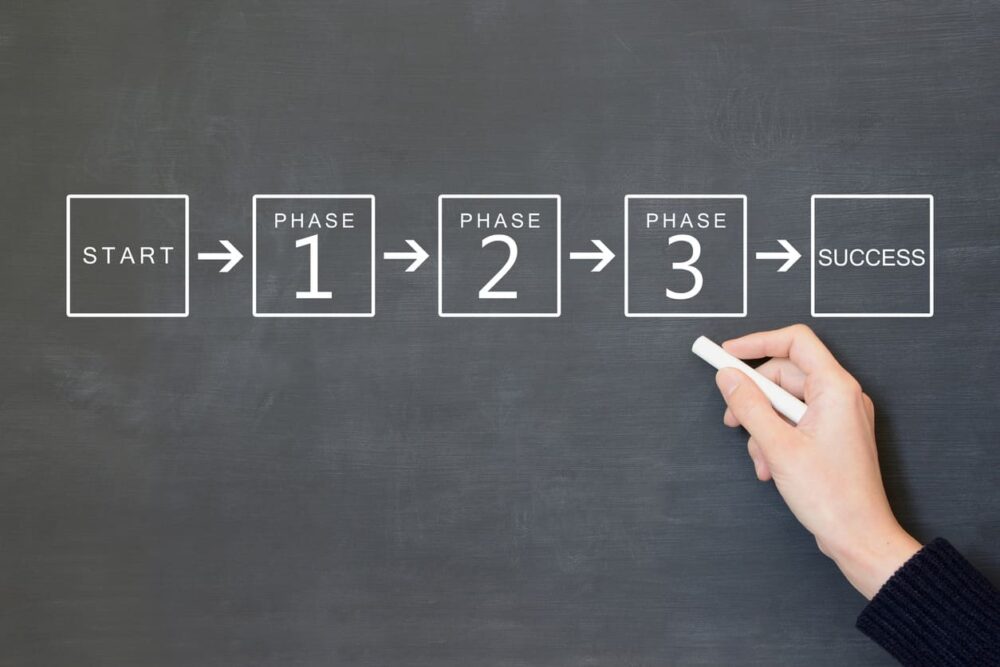
注文住宅を建てる流れは土地なしの場合、引渡しまでで次の8ステップです。
- 予算検討
- 住宅のイメージを作る
- 依頼する業者を厳選して土地を探す
- プランの作成と見積もり
- 工事請負契約
- プランの詳細な打ち合わせ
- 着工
- 竣工と引渡し
土地有りの人は土地探しが不要となるだけで、その他の流れは土地なしの場合と同様です。
STEP1:予算検討
注文住宅を建てる第一歩は予算検討です。自己資金や住宅ローンを活用して、いくらまでなら日常生活に支障がでないのかで、土地代や建物代にかけられる総額の目処を立てましょう。
住宅ローンの月々の返済額については、金融機関などがシミュレーションツールを用意しています。借入額や金利、返済期間を入力すると、結果が自動的に算出されるので参考にしてください。
予算検討では、ライフプランを作成して将来の出費も含めたシミュレーションも必要です。住宅ローンは長いもので返済期間を50年に設定できるものもあります。現在の出費では問題なく返済できても、子供の教育費の増加や両親の介護、退職後の収入低下などがあり得ます。できるだけ具体的な数字で予算検討をしましょう。
関連記事:住宅ローンはどこに相談すべき?相談窓口の種類と相談する際の注意点
STEP2:住宅のイメージを作る
住宅のイメージは、施工会社へ相談する前にある程度固めておくと、スムーズなプラン作成につながります。曖昧なイメージだけでは、担当者もアドバイスをしにくいでしょう。
イメージ作りをする際は、家族でじっくりと話し合ってください。土地なしから始める場合は、次の項目を抑えておくとよいです。
- 通勤や通学の利便性はよいか
- 周辺に生活に必要な施設はあるか
- 治安や環境はよいか
- 地盤は固く地盤沈下や液状化の心配はないか
- 災害のリスクはどれだけあるか
- 日当たりや風通しはよいか
- 外観のデザイン
- 間取り
- 動線
- 導入する設備
些細なことでも希望を書き出し、実現したいことの優先順位をつけましょう。かけられる予算には限度があり、すべての希望を満たせる土地が見つかる保証はありません。予定している時期までに注文住宅を完成させたいならば、妥協は必要になってくるでしょう。
STEP3:依頼する業者を厳選して土地を探す
土地探しは、不動産ポータルサイトを利用すると簡単に希望の条件で絞り込んで検索できます。不動産ポータルサイトは誰でも気軽に利用できますが、中にはインターネット上には公開されていない情報もあるため、直接業者や担当者への問い合わせもおこないましょう。
土地探しには数ヵ月かかるケースもあるため、並行して注文住宅を依頼する施工会社も探してください。選択肢は大きく分けてハウスメーカー、工務店、建築設計事務所の3つあり、特徴は次のようになっています。
| 施工会社 | 特徴 |
| ハウスメーカー | ・対応地域は全国規模 ・自社生産で高品質の建材を使用 ・提供ブランドからデザインを選ぶ |
| 工務店 | ・地域の特性を熟知して設計 ・融通が利きやすい ・仕上がりは職人の技術力に左右 |
| 建築設計事務所 | ・設計の自由度が高い ・予算内で柔軟な対応 |
請求した資料の内容や内覧での現物、担当との相性を比較して、依頼先を厳選しましょう。なかには土地探しから建築後のメンテナンスまでおこなうワンストップサービスを提供している業者もあります。
土地が見つかれば売買契約を結びます。また、必要があれば住宅ローンの事前審査の申し込みもこのタイミングでおこないましょう。土地の引渡し時にお金が必要になります。
関連記事:ハウスメーカーの選び方とは?自分にピッタリ合う探し方を紹介
関連記事:ハウスメーカーと工務店の5つの違いとは?それぞれのメリット・デメリットと選び方
STEP4:プランの作成と見積もり
どの施工会社に注文住宅を建ててもらうのかは、プランの作成と見積もりの結果で最終的な決定をします。担当者に予算と理想の住宅の優先順位を伝えて、プランの提案をしてもらってください。
プラン作成や見積もりだけならば、基本的に無料で対応してもらえます。一部有料のところもあるため、公式サイトで最新の情報を確認してから依頼しましょう。
STEP5:工事請負契約
納得ができるプランや見積もりを出してくれる業者が見つかれば、工事請負契約を結びます。契約書には支払う総額を記載するため、注文住宅の間取りや仕様、設備などはほぼ確定した状態です。この契約が結ばれると、自己都合でのキャンセルには違約金が発生するのが一般的です。違約金は総額の3~10%が相場のため、慎重に決断をしてください。
住宅ローンを利用する人は、この契約書の金額を踏まえて本審査の申請をします。結果が出るまでに1ヵ月程度かかるため、早めに申請を済ませておきましょう。
STEP6:プランの詳細な打ち合わせ
壁紙や扉はどのような素材・柄にするのか、設備のメーカーや性能はどれにするかなど、プランの細かい部分について打ち合わせをしていきます。
建築設計事務所を利用している場合は、ある程度選択肢が決まっているハウスメーカーと違い、自由度が高く打ち合わせにも時間がかかるでしょう。
STEP7:着工
最終決定したプランで業者に建築確認申請をおこなってもらい、建築基準法などで問題ないと判断されたら注文住宅の着工開始です。どれだけの期間で完成するかは、選択した工法によって変わります。代表的な工法の種類と特徴、かかる期間は次のようになっています。
| 工法 | 特徴 | 期間 |
| 木造軸組工法(在来工法) | ・日本の伝統的な建て方 ・自由度の高い間取りが可能 |
4~5ヵ月 |
| 2×4工法(ツーバイフォー) | ・2×4インチで規格かされた建材を使用 ・工期が短いため施工費用も安い傾向 |
2~4ヵ月 |
| 重量鉄骨造 | ・厚さ6mm以上の鋼材を使用し高い耐久性を実現 ・広い空間を実現可能 |
4~5ヵ月 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | ・木造の2倍以上の耐用年数 ・高い遮音性・断熱性 |
5~6ヵ月 |
STEP8:竣工と引渡し
竣工したら、施工会社の立ち会いで不備や不具合がないかのチェックをします。必要であれば手直しをしてもらい、引渡しに進みましょう。
引渡しの前に、費用の精算と登記手続きをします。金融機関や法務局は土日や祝日は閉まっているため、平日におこなう必要があります。実際にかかる時間は1時間程度でしょう。
引渡し当日から新居で生活を始めたい人は、事前に引越しやライフラインの契約も済ませておきましょう。インターネットの回線工事だと、開通まで1ヵ月以上かかることもあるため早期の手配をおすすめします。
注文住宅を建てる際にかかる費用一覧

注文住宅を建てる際にかかる費用は、大きく分けて本体工事費・別途工事費、諸経費の3つです。国土交通省の調べによると、土地を購入した注文住宅新築にかかる費用の平均は5,436万円です。無駄な出費を抑えるためにも、内訳がどうなっているのかを把握しておきましょう。
“参考:国土交通省「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」”
本体工事費
本体工事費は、坪単価などで表現される次のような部分にかかる費用です。
- 仮設
- 基礎
- 構造体
- 屋根
- 内装
- 設備
総額の75%程度を占めており、広告に〇〇万円で建てられると書かれていても、実際は追加で25%ほどの支払いが必要になることが多いです。本体工事費は、材料費や人件費の高騰で影響がでやすいです。
別途工事費
別途工事費とは、建物本体以外で次の工事をおこなう際に支払います。
- 庭や塀などの外構
- 水道管やガス管の引き込み
- 照明やエアコンの取り付け工事
- 地盤の改良
- 解体工事
総額の20%程度を占め、こだわるほど費用は上限なく上がります。外構に関しては、建物の施工会社とは別に依頼する場合もあります。
地盤の改良は実際に調査をしないと、必要かどうかの判断は難しいです。土地探しの段階で、河川や海の近く、埋め立て地、高低差があるところなどを避けておくと、改良が不要になる確率は高まります。
諸経費
諸経費とは、注文住宅を建てるまでの手続きや、生活のために必要になるものをそろえる費用です。主に次のようなものがあり、総額の5%程度を占めています。
- 印紙税
- 不動産取得税
- 登記費用(登録免許税・司法書士への報酬)
- 仲介手数料(土地なしの場合)
- 建築確認申請費用
- 建築設計費
- 地鎮祭・上棟式の費用
- 住宅ローンの手数料・保証料・団体信用生命保険料
- 建てた住宅にかける火災や地震の保険料
- インテリアや家電の購入費用
- 引越し代
近年では諸経費もローンを組める銀行も増えてきています。
注文住宅を建てるときに必要な書類

注文住宅を住宅ローンで土地なしから建てる場合、次の書類が必要になります。
| 土地の購入 | 住宅ローン | 注文住宅の工事請負 |
| ・本人確認書類 ・印鑑証明書 ・住民票 ・実印 |
・本人確認書類 ・印鑑証明書 ・住民票 ・源泉徴収票・確定申告書 ・住宅ローンの申込書 |
・本人確認書類 ・印鑑証明書 ・住民票 ・源泉徴収票・確定申告書 ・間取り図・見積書 |
本人確認書類は、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなどが該当します。コピーは使えませんので原本を用意してください。
印鑑証明書や住民票は、発行から何ヵ月以内のものと指定されるかもしれません。複数枚必要ですがそれぞれの手続きで期間が空くため、その都度発行したほうが確実です。マイナンバーカードを取得していると、役所に行かなくとも最寄りのコンビニなどでいつでも発行可能です。
注文住宅でお金が必要なタイミング

上記で紹介した注文住宅を建てる際の費用を支払うタイミングについて解説します。費用の支払いが必要になるタイミングは以下のとおりです。
- 工事請負契約までに支払う費用
- 着工・上棟時に支払う費用
- 引き渡し以降に支払う費用
費用が不足していると次のステップに進めないため、余裕をもって用意しておきましょう。
工事請負契約までに支払う費用
土地なしから注文住宅を建てる場合、工事請負契約以前に支払う費用は次の8つです。
- 土地の所有者への手付金・頭金
- 土地の費用の残金(住宅ローンで)
- 土地の売買契約書の印紙税
- 不動産会社への仲介手数料
- 土地の所有権移転登記の登録免許税
- 登記手続きを司法書士に依頼した際の報酬
- 固定資産税の日割り
- 工事の契約金
登記手続きは、自力でおこなうことも可能です。法務省の登記・供託オンライン申請システムを利用すると手間はかからず、役所が閉まっている平日18時以降でも処理をしてくれます。少しでも出費を抑えたい人は検討してみましょう。
着工・上棟時に支払う費用
着工から上棟までに次の9つの費用の支払いが必要です。
- 解体費用(土地に建物がある場合)
- 地盤調査費用
- 地盤改良費用(必要であれば)
- 着工時金(本体工事費の30%程度)
- 建築確認申請費用
- 建築設計費
- 上棟時金(本体工事費の30%程度)
- 地鎮祭・上棟式の費用
- 住宅ローンの手数料・保証料・団体信用生命保険料
自己資金の出費を抑えるならば、解体費用も住宅ローンに組み込んでおくとよいです。東京での相場だと1平米あたり3~8万で、1975年より前の建物はアスベストの調査も求められ費用はさらにかかります。
解体工事会社の選び方や流れを詳しく知りたい人は、次の記事もおすすめです。
関連記事:【2023年最新】東京でおすすめの解体工事会社11選!選び方のポイントも
引き渡し以降に支払う費用
引渡し以降では、次の9つの費用を支払います。
- 完成時金(本体工事費用の残額)
- 建物の登記費用
- 不動産取得税
- 引越し代
- 火災や地震の保険料
- インテリアや家電の購入費用
- 固定資産税・都市計画税(購入した翌年に納税)
- 住宅ローンの返済(引渡しの翌月から)
- 外構費用
外構工事を別業者に依頼した場合、住宅ローンに含められないケースがあります。リフォームローンやフリーローンは使えますが、金利は住宅ローンより高くなるので注意が必要です。
また建てた注文住宅のメンテナンス費用は、賃貸と違いすべて自己負担です。10年や20年後を見越して、計画的に貯蓄をしましょう。メンテナンスを怠ると、住宅は傷みやすくなります。
注文住宅を成功させるための注意点

最後に注文住宅を成功させるために、次の4つの注意点について解説します。
- 期間に余裕を持つ
- 本契約時は内容をきちんと確認する
- 追加で工事が必要になる時がある
- 土地によって制限がある
なにも知らずに家づくりを進めていると、予定時期に完成しなかったり出費が増えたりする可能性が高まります。
関連記事:戸建て購入時に確認する17の注意点|新築・中古別にデメリットも紹介
期間に余裕を持つ
注文住宅を建てるまでの期間には余裕をもっておかないと、中途半端に妥協をして後悔をしてしまいます。特に土地なしの状態から注文住宅を計画すると、そもそも希望の土地が見つからず時間がかかる場合もあります。優良な不動産会社に依頼をしても、希望に合うものが売りに出されていなければ、どうにもなりません。期間に余裕がないと、優先順位が上位の条件であっても満たせない可能性があります。
プランの作成でも、急いで決めてしまうと住み始めてから不満を抱くかもしれません。また、着工から竣工までの期間に台風シーズンが含まれていた場合、天候次第で工期は延びます。想定よりさらに数ヵ月かかる可能性を考慮して、早めに注文住宅計画を進めていきましょう。
本契約時は内容をきちんと確認する
土地の売買契約や工事請負契約は、締結されると制約なしでキャンセルはできないため、内容をきちんと確認してください。
契約前に確認するべき内容は、主に次の4つです。
- 対象となる不動産の状態
- 契約の条件
- キャンセル時の対応
- 支払いのタイミング
専門用語が多く難しいと感じたら、きちんと担当者に質問をして、気になることや疑問はすべて解消しましょう。
追加で工事が必要になる時がある
着工してからでもプランの修正が可能な場合もあります。しかし追加で工事が必要になったり、費用や期間が増えたりすることを知っておきましょう。
増えた費用に合わせて住宅ローンの融資額を変更するのは難しいため、できるだけ追加の工事が必要にならないよう、工事請負契約の段階で細部までプランを詰めてください。
土地によって制限がある
土地を探す際は、立地や広さだけでなく法律による制限にも注意をしてください。主な制限に次のものがあります。
| 種類 | 概要 |
| 用途地域 | ・建てられる建物の種類を制限 ・種類によって住宅は建築不可 |
| 建ぺい率 | ・敷地面積のなかでどれだけ建物の面積として使えるかの制限 ・基本は30~80% |
| 容積率 | ・建築可能な建物の床面積の制限 ・基本は50~500% |
| 斜線規制 | ・通気性や採光性を確保するための高さ制限 ・道路・隣地、北側の3種類 |
| 接道義務 | ・建物を建てるなら敷地は4m以上幅がる道路に2m以上接している必要 ・接道義務を満たせない空き家を解体しても再建築は不可 |
これらの制限を知らずに土地を購入すると、希望の条件で注文住宅を建てられない可能性があります。不動産会社に探してもらう際、建てたい住宅のイメージも伝えておくと、候補は絞り込みやすくなるでしょう。
関連記事:土地を安く買う10の方法を徹底解説!土地探しから税金対策まで
関連記事:土地の価格の調べ方とは?目的別のおすすめ手法や計算式を紹介
【体験者インタビュー】注文住宅の依頼経験がある方に詳しく聞いてみた
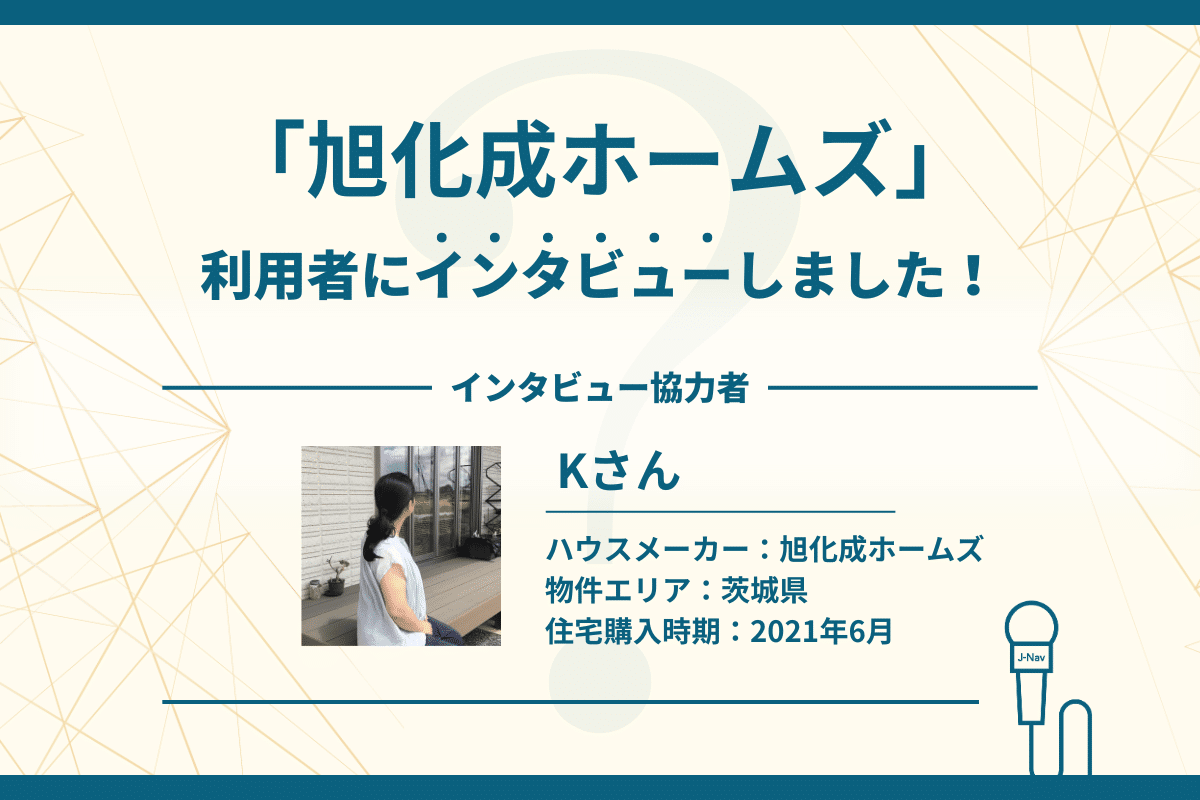
注文住宅を建てたいと考えて、まずどのような行動を取られましたでしょうか?





ご自身ではネットなどで調べながら資金計画を建てられた形でしょうか?



次にどれくらいの予算か、間取りの希望を聞いて、おおまかな設計図を作ってもらいます。そこへ展示場でもらった資料や、気に入ったモデルハウスなどの取り入れたい特徴を伝えて、反映させてもらいます。その過程で、たびたび強度の計算というものがあり、希望する間取りがヘーベルハウスの基準を満たす強度を出せるか、間取りのどこを譲るかなど、足したり引いたりして検討しました。


住宅ローンの控除は利用されましたでしょうか?



まとめ
注文住宅を建てる流れには、予算検討から引渡しまでで8つのステップがあります。土地探しから始めると10ヵ月から1年半程度かかり、期間に余裕をもっておかないと、妥協が増えて不満が残るマイホームになってしまいます。
スムーズに手続きを進めるため、全体の流れを把握し契約は細部まできちんと確認してください。段取りを事前に頭に入れて早め早めの準備を心がけることで、納得いく注文住宅の完成につながるでしょう。

